機動戦士ガンダム00
暗灰色の夜明けに
登場人物
ハレルヤ・ハプティズム
超兵研究所の被験体E−56。凶暴で攻撃的な性格の持ち主。
アレルヤ・ハプティズム
超兵研究所の被験体E−57。優しく穏やかな性格の持ち主。
マリー
研究所で生まれ、育てられた少女。
アンドレイ
研究所の教官。
グェン
ソレスタル・ビーイングの工作員。
ロックオン・ストラトス
ソレスタル・ビーイングのMSパイロット。
本編
ATROPOS―ハレルヤ・ハプティズム―
俺達は何も感じない。
全てを失ったあの時、俺達の心は死んだんだ。
だから、お前等がやっていることには、なんの意味もない。
音も光もないこの部屋に閉じ込め、拘束衣で体の自由を奪い、糞尿を垂れ流す。
それがなんだというのだ。
こんなことで俺達をどうにか出来ると思っているのなら、とんだお門違いだ。ましてや壊れてしまうような心など持ちあわせちゃいない。
何も感じない俺達には、退屈な日常と変わらない退屈な状況でしかない。
扉の開く音がして、光の筋が部屋に差し込み、五人分の人影が中に入ってきた。
教官どもだ。
その内の一人が俺の目の前に立った。
熊のようにでかいロシア人―教官仲間からアンドレイと呼ばれていた―が、サディスティックなニヤニヤ笑いを顔に浮かべている。
「どうだ、少しは反省したか?E−56」
悪態の一つでもついてやろうと思い、口を開けたがやめた。もっと面白いことを考えついたからだ。
俺は哀願するような目で口をパクパクさせ、聞こえるか聞こえないかの声を出した。
「どうしたE−56。いつものお前らしくないじゃないか。まさかぶっ壊れちまったんじゃないだろうな」
熊のアンドレイはバカデカイ体を折り曲げ、椅子に縛りつけられている俺の口元に耳を寄せた。
「何を言ってるんだ。もっと大きな声で言わないと聞こえないじゃないか」
俺は口元に笑みを浮かべた。
いいポジションだ。
「バーカ」
俺はそう言うと、奴の右耳に思い切り噛み付いてやった。
首を捻り、一気に耳を引きちぎる。
ブチブチという小気味良い音とともに、鮮血が迸った。
熊のアンドレイは豚のような悲鳴を上げ、右耳のあったところを手で押さえながら地面に勢い良く転がった。
「マジィー」
俺は噛み千切った耳を床に吐き捨てた。
「耳が!俺の耳が!」
血まみれのアンドレイが床を転がり回っている。
他の四人は何が起こったのか状況判断が出来ずに、ポカンと口を開けたまま立ち尽くしている。
俺の口から笑いが漏れた。
我慢が出来ない。
俺はその光景を見ながら笑い続けた。
俺の笑いで四人の教官の顔色が変わる。
四人は腰の警棒をそれぞれ手にとっていた。
やっと状況が理解出来たようだ。
四人がゆっくりと近付いて来る。
俺は四人の顔をじっくりと見た。
逆光で細かい顔の判別は出来ないが……まあ大丈夫だろう、この部屋を出たら研究所の端末に忍び込んで調べればいい。
どうせこいつらの死刑は確定なのだ。
アンドレイの方を見た。
奴はこのリンチに加わるつもりはないらしい。
手で耳を押さえたままうずくまり、体を小刻みに震わせながら泣いている。
こいつは他人の痛みには鈍感なくせに、自分の痛みには耐えられない,情けないクソ野郎のようだ。
使えそうだ、無罪。
そんなことを考えているうちに、四人の教官達の足は止まり、手の警棒は俺の頭上高く振り上げられていた。
「悪いなぁ、アレルヤ……」
LAKHESIS―ロックオン・ストラトス―
ロックオンはティエレンのコックピットハッチを開けて煙草をくゆらせていた。
出撃前の緊張感は特になかった。
馴れというよりも麻痺に近い感覚なのかも知れない。
殺した人間の数、MSに乗った回数、こなした作戦、いつしか数字は意味をもたなくなり、数えることが億劫になっていた。
引き金を引く度に近づけると思っていたものがなんだったのか……今ではその輪郭すら、ぼやけてしまっている。
力が欲しかった。
復讐するために。
理不尽な何かに蹂躙されるだけの存在でいないために。
世界を敵にまわしたとしても……。
その時、ロックオンの思考を遮るかのように、ティエレンの通信用モニターに映像が映る。
「そろそろ用意しな」
貧相な顔をしたクメール人がそこにいる。
「出撃?」
「そうだ。今からきっかり十五分後。狙撃地点に着いたら警備のティエレンを狙撃、三分後に終了。すぐに別働隊が突撃する。後は……好きにしな」
「了解した」
「質問は?」
ロックオンは少し考えるような素振りを見せると、口を開いた。
「なあグェン、あんたは何のために戦っているんだ」
「そいつが質問かい」
「そうだな、他に何も浮かんでこなしいな」
グェンはクッと鼻で笑った。
「俺の体にはクメール・ルージュの血が流れている。その血が囁くんだよ。コロセ、ブンナグレ、ってな。ソレスタル・ビーイングの思想に共鳴してるのは確かなんだがな……けど実際のところ、俺の中の色んなもんがぼやけちまってるからな。何のためにって聞かれても、血が囁くってことぐらいしか答えようがないな」
ロックオンはグェンの言葉を聞き、彼と同じようにクッと鼻で笑った。
「ロックオン、あんたはどうなんだ?」
「俺かい?俺は……忘れっちまったな」
「そうか、まあ、そういうこともあるさ」
「そういうこともあるよな」
ロックオンは呟くと煙草を外に捨て、コックピットハッチを閉じた。
ATROPOS―アレルヤ・ハプティズム―
目を開けると、そこに天使がいた。
心配そうに僕の顔をのぞきこんでいる。
「ここは……」
僕が呟くと、天使―少女の顔が微笑みに変わった。
「医務室よ。大丈夫?」
僕は起き上がろうと体を動かした。
痛みが全身を貫く。
筋肉と間接、神経の全てが悲鳴を上げる。
「無理しちゃダメよ」
僕はその言葉を無視して、なんとか半身を起こすことに成功した。
痛みのせいで全身から汗が噴出す。
「君は……誰?」
顔に無理やり笑顔をつくり尋ねた。
「ちょっと待ってて」
少女は言うなり身をひるがえして部屋の奥へ消えた。
少女の姿を目で追おうとして首を動かすと、凄まじい痛みが全身に広がった。
思わず悲鳴が出そうになるのをこらえ、目を閉じて歯をくいしばる。
ふと、顔に柔らかい布の感触を感じた。
少女が僕の顔の汗を拭いてくれている。
「だから無理しちゃダメって言ったでしょ」
「ごめん」
少女は僕の顔の汗を拭き終わると、傍らの椅子に腰掛けた。
「私はマリー。あなたは?」
「僕はE−57」
少女は顔を曇らせた。
「そっちじゃなくて、あなたの本当の名前よ」
「本当の名前……」
ここに来てからの僕はE−57と呼ばれた。孤児として生きて来た僕は名前を持たなかった。ただある時期、ある名前で呼ばれたことはある。引き裂かれた僕の半身……あの人は僕をその名で呼んでくれた。
「アレルヤ……」
「アレルヤ?」
「そう、アレルヤ」
「それがあなたの名前」
僕は頷いた。
そう、それが僕の名前だ。
LAKHESIS―ロックオン・ストラトス―
ロックオンのティエレンは研究施設を見下ろす小高い丘の上で待機していた。
ティエレンの頭部には長距離射撃用の砲塔が一門、聳え立っている。
ロックオンのスコープは、既に敵の姿を捉えている。
ロックオンは腕時計を見た。
「あと、五分」
後は引き金を引くだけだった。

ATROPOS―アレルヤ・ハプティズム―
僕はどちらかと言うと強い方じゃない。
元々、体だって強い方じゃないけれど、あの日以来……マリーと出会ってから、僕は何かと医務室に行くことが多くなった。
ああ、ハレルヤ、君は知っていたのだろうか?
僕がマリーのことを想い、いつもそれだけを考えていたことを……
僕が医務室に運ばれると、いつもそこにマリーの笑顔があった。
運命―神の手―そんなモノよりも、もっと淡い何かが僕の胸を満たして行く。
永遠に続くかと想われた逢瀬。
けど今日は違っていた。
そこにマリーの姿はなかった。
僕が眼を覚ましたベッドの傍らに一枚の紙片が置かれていた。
“サヨナラ”
そこにはただそれだけが書かれてあった。
僕は眼を閉じてマリーの笑顔を思い出そうとした。
なぜだろう?
うまくマリーの顔を思い浮かべることが出来ない。
僕は永遠にマリーを失ってしまったのだろうか……。
胸の中で、不吉な黒い翼を持ったなにかが、大きく羽を広げていた。
LAKHESIS―ハレルヤ・ハプティズム―
眼の前に醜く太った老人がふんぞりかえっている。
俺の殺意は限界まで膨れ上がっていた。
その醜悪さ万死に値する。
「全く、君には困らされるな。所長の私の力にも限界はあるんだよ。いくら君が優秀だからといってもねえ」
「なんのことですか?」
「とぼけるんじゃない!君だろ!君がやったんだろ!四人もの教官を殺したのは君だろ!」
「証拠、あるのかい」
「そんなものはない。ないが……犯人は貴様に決まっている―」
俺はこんな意味のない会話に飽きていた。
もちろん、殺ったのは俺だ。
けど証拠なんて何一つ残しちゃいない。
俺が口を割らない限り、奴らは俺をどうすることも出来ないのだ。
そうそう、こいつは気付いちゃいないが、俺が殺ったのは五人だ。
イマイチ使い勝手が良くなかったので、アンドレイもついでに始末したからな。
さて、今度はどうやってこいつを殺そうか。
今、俺の頭の中を支配していたのは純粋な殺意だけだった。
とりあえず、自分の右手の親指の間接を外しておく。
後ろ手に手錠をかけられていては、行動に制限がある。
こうしておけば、いつでも手錠から手を抜くことができるからだ。
その時だった、窓の外に映る夜景が一瞬にして昼間のような明るさに変わった。
轟音とともに建物全体を振動が襲う。
「な……なんだ」
所長の顔に狼狽が走る。
チャンス。
なんだか知らないがこいつを利用させてもらおう。
俺は一気に所長との間合いを詰めると、そのまま顔面に前蹴りをぶち込んだ。
鼻骨のひしゃげる感触とともに、所長は椅子ごと後ろに倒れこむ。
俺は素早く手錠から右手を引き抜き、親指の間接を左手で無理やり押し込んだ。
鈍い痛みが脳天に走ったが、そんなことに構っている暇はなかった。
俺はデスクの上にあった万年筆を掴み、倒れている所長の上に馬乗りになった。
首筋に万年筆の筆先をつきつける。
「立て」
俺は所長の胸倉を掴み、無理やりに立たせると、万年筆を突きつけたまま背後に回り込む。
その時、所長室の扉が開き、三人の警備兵が部屋に入って来た。
「所長!大変です!てきしゅ……う、貴様っ何をしている!」
三人の警備兵が一斉に自動小銃の銃口をこちらに向けた。
また轟音が響き、建物が揺れる。
「お……お前達、何をしてる。早く私をたすけんか!」
三人の警備兵は動こうしてやめた。
所長の首筋に当てられた万年筆に気づいたようだ。
「おまえら、銃を下ろして、こっちに向かって投げろ。馬鹿なことは考えるなよ。おまえらが何かする前に、この豚はあの世行きになっちまうぞ」
三人は素直に俺の指示に従い、自動小銃を俺の足元に放り投げた。
その内の一丁を拾い、警備兵に銃口を向ける。
「三人とも、両手を壁につけて並べ」
三人はこちらに背を向けて並んだ。
「それでいい」
俺は自動小銃のセレクターをフルオートにし、三人の背中に向けて引き金を絞り込んだ。
血煙を上げながら、三人は床に沈んでいった。
それを見た所長が悲鳴を上げる。
「うるせえ、お前もやっちまうぞ」
LAKHESIS―ロックオン・ストラトス―
ロックオンは四機のティエレンを破壊したところで狙撃をやめた。
時間が来たのだ。
頭部に装備していた長距離砲のロックを外すと、それを掴んで地面に捨てる。
「さて、行きますか」
ロックオンは呟くと、研究所に向けてティエレンを発進させた。
LAKHESIS―アレルヤ・ハプティズム―
僕は死ぬのだろうか。
何度目かの地響きが聞こえた後、部屋に警備兵が入ってきてその手に持った銃で僕達を撃ち始めたのだ。
銃声と悲鳴が響き渡り、僕は腹に三発の銃弾を受けた。
鮮血と内臓をまきちらし、僕は地面に倒れている。
意識が遠くなって行く。
ほんの一瞬だがマリーの笑顔を思い出したような気がした。
けれど一瞬の蜃気楼のように淡く消えてしまった。
頭に残っているのは誰の姿だろう。
ああ、あれは引き裂かれた僕の半身、懐かしいあの人の姿だ。
さよなら、さよなら、ハレルヤ。
LAKHESIS―ハレルヤ・ハプティズム―
どこをどう走ったのだろうか。
いつしか俺は外に出ていた。
研究所は散々に破壊されている。
邪魔なので所長は途中で捨ててきた。
やっと、ここから逃げ出せる、そう思ったのに……アレルヤ。
俺はどうすればいい。
俺に残っていたのは、お前だけだったのに。
俺はその場にしゃがみこんだ。
もう、どうでもいい。
もう……。
KLOTHO―ソレスタル・ビーイング―
ロックオンのティエレンが一人の少年の姿を捉えた。
おそらく研究所の被験体だろう。
ロックオンは少年の前でティエレンを止めるとハッチを開けた。
「大丈夫か」
少年は顔を上げた。
金色の瞳には光がなく、空ろなガラス玉のようだった。
「名前は?」
「なまえ?」
「そうだ、自分の名前だよ。言えるか?」
「E−56」
「違う、そっちじゃねえ。本当の名前だよ」
少年は少し逡巡を見せた後、苦痛をこらえるかのように、目を閉じた。
「名前、本当の名前……」
少年の言葉を、ロックオンは我慢強く待っていた。
数秒の沈黙の後、少年はゆっくりと目を開け、ロックオンを見つめかえした。
少年の目に光が甦っていた。
しかし、その瞳の色は暗灰色に変わっている。
「名前、僕の名前はアレルヤ、アレルヤ・ハプティズム!」
いつしか夜は明け始めていた。
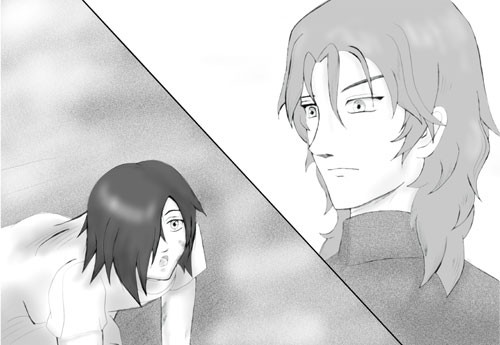
暗灰色の夜明けに 完